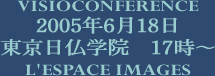ジャン・ドリュモー(Jean
Delumeau)
1923年生まれの、アナール派第三世代に属するフランスの歴史家。パリ・ユルム街の高等師範学校出身。パリ第1大学教授を経てコレージュ・ド・フランス教授(1975-1994年)。中世後期から近代にかけての西欧宗教思想史、とくに宗教心性史を自己の領域としている。カトリシズムを思索の基盤としつつ、現在に至るまで旺盛な執筆活動を展開。主要著作に『ルターの時代からヴォルテールの時代にかけてのカトリシズム』(1971年)、『恐怖心の歴史』(1978年、邦訳1997年新評論刊)、『罪と恐れ』(1983年、本書)、『慰撫と加護』(1989年、邦訳『安心と加護』新評論近刊)、『告白と許し』(1990年、邦訳2000年言叢社刊)、『楽園の歴史(三部作)』(1992、1995、2000年、第一部『地上の楽園』邦訳2000年新評論刊、第二部『至福千年』[邦訳『千年の幸福』新評論近刊]、第三部『楽園が残したもの』)などがある。最新刊は、Le
fait religieux, t.1 et 2, 09/2004 Fayard.
『罪と恐れ』は日本語に訳された四番目の私の著作です。私はこのことを幸せに思いますし、また誇りにも思います。それ以前に訳された著作に『恐怖心の歴史
』、『告白と許し』や『地上の楽園』があります。
現在に至るまでの長い間、研究の進んでいない幾つかの「歴史学の対象」の中には、もっと人々の関心を引くべき価値があるもの、さらに、その対象同士の関連性を解明することの待ち望まれているものがあります。こういった作業こそ、私が(28歳からの)長い調査活動を通じて行ってきたことなのです。第一の対象は「恐れ」でありました(『恐怖心の歴史』1978,
『罪と恐れ』1983)。二番目は安心感でありました(『安心を与えることと守ること』1989, 『告白と許し』1990)。そして三番目には「楽園の歴史」というタイトルを付けましたが、それは3つの部分に分かれています。『地上の楽園
』(1992)、『幸福の千年』(1995)、『「楽園」には何が残っているか』(2000)の三冊です。恐怖、安心感への欲求、幸福への希求というテーマに関して、実際私が行ったのは、信仰や集団的表象の歴史を、リュシアン・フェーヴルやフィリップ・アリエスらの業績、すなわち広く意味での「アナール学派」の仕事の後を継ぐような形で詳述するということでありました。
これらの仕事はすべてキリスト教世界に限られています。しかし私の頭の中では、これらの仕事は、西洋文明以外の文明にも導入することが可能な比較研究となるべきものなのです。『罪と恐れ』を出版するとすぐに私は、チュニス大学からこの本について話して欲しいという講演依頼を受けました。この依頼の狙いはまさに、西洋の罪の感情とイスラムの国々で人々が抱いている過失の感情を比較してみるということにあったのです。
しかし、この本を書くことを通して、私は人々に見過ごされがちな歴史的特異点を描き出そうと試みました。つまり、13世紀から18世紀にかけてのキリスト教文明ほどに罪の意識や悔恨の念に重きをおいた文明はなかった、ということです。まさに私たちはいくら解明してもしすぎることのない重要な事例を目の前にしているのです。ある特定の空間と時間における罪の歴史、つまり自身に関する「悪いイメージ」を見出すということは、人間世界の真ん中に身を置くということであり、集団的精神性を構成する関係性の総体を引き出すということであり、人間の自由そして生と死に関する社会の深い思考を見出すということであり、「神」と如何に関わっているかについての概念とその概念がその「神」からどのような表象を引き出しているかを発見するということなのです。ということは、すなわち、ある限られた時間と空間の中に、「神」の歴史と人間の歴史を同時に見出そうとすることなのです。「神」とは極めて良きもの、正しいものではないのか?1つの文明全体が何世紀にも渡ってこの疑問にねばり強く取り組んできたのです。
フロイトとユングは互いに嫌い合っていましたが、社会に関する研究はすべからく罪に結びつけて考えるべきである、としていた点では一致していました。フロイトは罪悪感を文明の主要な問題として提示しました。そのことを考えれば、何故私が西欧の歴史における罪悪感の問題に関して厚い本を書いたのかがわかって貰えるでしょう。ユングは「意識と覚醒を呼び起こすのに自分自身とのずれの感覚ほど適切なものはない。」と書きました。
自分の意識を問い直そうとすることによって、人は長い時間をかけて、内省を、前例がないほどまでに洗練させていったのです。それは個人の責任の感覚をどんどんと研ぎ澄ましていきましたし、それによって強く個人主義の発展を促しました。それは意志決定におけるモラルを発展させたのです。それは言い落とされたことには重要なことがあるということを気付かせてくれました。徹底的な罪悪感に従うキリスト教徒は自分の過去に意識的になり、自分のアイデンティティを正確に把握するようになったのです。「後ろめたさの意識」は、必然的にその対立項として現在では我々の精神的道具になっている「情状酌量」の観念を熟成させました。更に、心理学のレヴェルで、告白は、それが自由で自発的である限りにおいては、孤独を癒し、人の意見に耳を傾けることを可能にし、苦しみを他人と分かち合うようになるということ、そして許しは喜びと自由を罪悪感で押しつぶされそうになっている人たちに与えるということを付け加えておかなければなりません。私の『罪と恐れ』という著作は、なにも罪悪感を否定し非難しているわけではないのです。しかし恐れを扱う歴史家にとって、過去において西欧文明が過剰なまでに罪悪感を利用してきたということは見逃すことが出来ませんでした。私が「過剰な罪悪感」ということで言いたいのは、許しに比べて罪の規模が大きすぎるということです。この不均衡は、それ自体で、私の研究の題材となっています。また私は読者の皆さんに、全体の三分の一ほどにあたるこの本の第1部は、まさに「ルネッサンスのペシミズム」を扱っているということを喚起しておきたいと思います。この「ルネッサンスのペシミズム」という表現は、読者を驚かせてしまうかも知れませんが、私がルネッサンスに関して行ってきた研究のすべてを要約しています。私はルネッサンスに関して、『ルネッサンスの文明』(1967,
1973と1981に再刊)という本を書いていますし、他の著作のほとんどが15世紀から16世紀にかけての時代に多くのページを割いています。この時代のことを調べることによって、私はルネッサンスが単に祝祭のイメージだけではなく、素晴らしい芸術の出現という現象に要約されるということがわかりました。混乱と不安の時代であったルネッサンスはプロテスタントの改革を産み、トルコの進出に脅威を感じ、魔法使いやユダヤ人を追い払いました。当時多くのキリスト教徒は逼迫した恐怖の中に生き、自ら「最後の審判」を予告しました。時間の主要なメディアである説教よって、人間はあまりに罪深いものなので死後に地獄で裁定者である厳しい神に断罪されなければならないだろう、と、人々は信じ込むようになったのです。ルターの異議申し立てとその成功は、当時受け入れられていたこの苦悩を無視しては理解できないでしょうし、またこの苦悩は特に宗教戦争という形で表出しました。ですから私の『罪と恐れ』という著作は特にルネッサンスと呼ばれる時代を照らす新たな照明なのです。
Jean Delumeau, Renne, 2005年3月




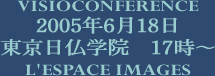
受賞経歴
1962年、国立科学研究センター、銀メダル
教育功労賞第3等受賞
芸術文芸勲章第3等受賞
レジオンドヌール勲章第4等受賞
功労賞第4等受賞
1968年、『ルネサンスの文明』で、フランス学士院ゴベール大賞
1977年、『キリスト教はやがて死ぬのか』で、カトリック作家大賞
1980年、フランス学士院モンティヨン賞
1981年、パリ市歴史大賞
1984年、フランス学士院マルセル猊下賞
1984年、ポルト大学名誉博士
1985年、ローマ市金メダル
1986年、『私の信ずるところ』で、フランス語信仰作家協会賞
1986年、シェルブルック 大学名誉博士
1986年、文化省「歴史大賞」
1992年、リエージュ大学名誉博士
1996年、デウスト大学(サン・セバスティアン-ビルバオ)名誉博士